スポーツだけではないが、選抜システムというのは、どの世界でも
問題が多そうだ。
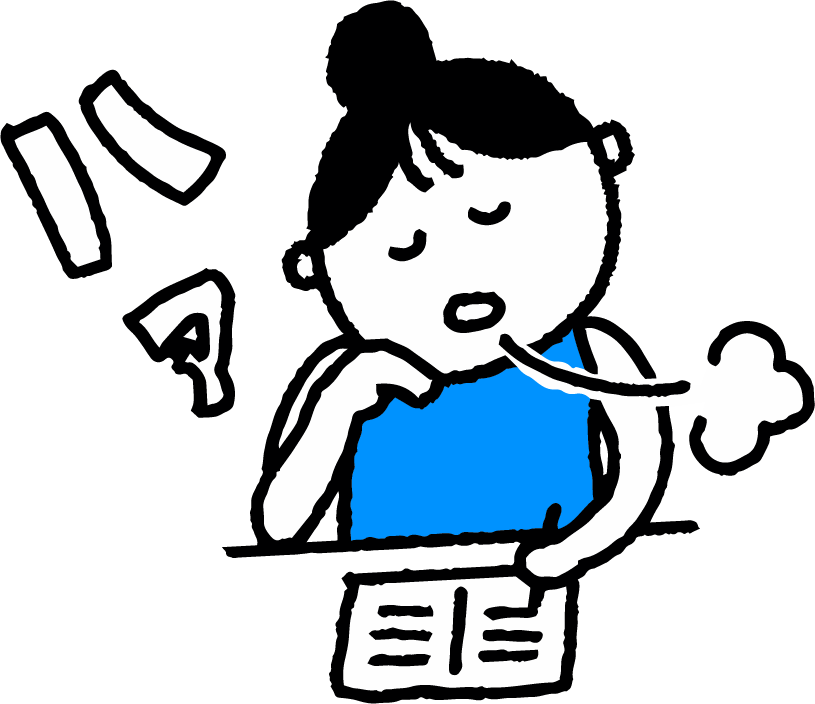
現実にフィギュア界でも、北京五輪の代表選考は物議を醸した。
平昌前にも問題になったが、微妙だが、少しずつ変わってきているし、
シングル男子と女子が違っていた時もあったように記憶しているが、
それは枠の数の問題だった気がしている。
正直、あの頃の男子はどうやっても羽生さんと昌磨しか考えられなかった。
二人がどうやっても、他の選手に負ける、なんて事は想定できなかった。
そう。棄権でもない限り。
でもよく考えたら、全日本を棄権する、ということは、その二か月後の五輪に
間に合うはずがないのだ。
真央ちゃんたちの時代は問答無用だった。
それは替わりの選手がいたからか?
実力が拮抗している時代だったとは言え、過酷だ。
でも、体操界でも同じ事が起こっていたし、大会二か月前に怪我をして、
その大会にベストパフォーマンスができる、なんて事は実際あり得ない。
あり得たとしたら、それはその時、棄権するような状態でなかったという事なのか。
でも、それでも他の選手より優れている、という選考をするなら、全日本の後で
テストスケートでもやるとか考えればいいが、まぁ、ピーキングができなかったという
段階で、選考から外すしかないと思うのだが。。。
その話はまぁ、他に色んな問題が出てきそうであるので、この辺にしておくが、
元陸上選手の為末さんが、ブログで語っていたのを興味深く読んだ。
まず大前提として選ぶことは力を行使することだということです。選ぶ側は常に選ばれる側よりも強い立場に立ちます。そこに選ばれたいと思う人が多く、その思いが強いほど権力は強くなります。ゆえに選び方に一定の制約を設ける事が多いです。その制約のかけ方により「選抜力学」は変化します。
選ぶ側が強い立場にいる。それはそう。
①選抜基準は明確か曖昧か
②選抜する側の人数が多いか少ないか
③選抜する対象は広いか狭いか
④選抜して手に入るものは希少かそうではないか
これによって選抜の様相は随分と変わります。
①については、陸上でも存在するのか、とびっくりした。
でも、何かで見た気もする。
前になかった、世界ランキングを見るようになったこと。
海外留学している選手に不利になっている、みたいな事です。
某選手に対して有利な選考になっている、と。
さらに為末氏は次のように述べている。
曖昧な基準による恣意的な選抜は長期的にそのグループを弱くします。実力を高めることよりも選抜者への忖度が生まれ、誰かに気に入られたり選ばれやすいグループに入ることを優先するので、競争が歪んだり競争が緩んだりするからです。(為末ブログ)
耳の痛いご意見です。
曖昧な基準による恣意的な選抜・・・・
まさに全日本の女子の選考がそうだったと言えるのではないかと思いました。
全日本一発勝負というなら、そうしておけば問題ないのに、世界ランキングやベストスコアだったり、色んな項目を入れておいたのに、発表の際は、若い世代に頑張ってもらうという新しい基準をぶっこんできた。
その説明センスが頂けなかった。
平昌の時から入ったシーズンランキングについては、
その時の記事にこう書いてあった。
世界ランクは、3シーズン分の成績で出されるため、シニアデビューしたばかりの選手が上位に入るのは難しかった。今回、新たな条件が加わったことで、来季、シニアデビューの本田真凜(大阪・関大高)や坂本花織(神戸ク)らにとっては可能性が広がる。小林芳子フィギュア強化部長は「若い選手がシニアに移行しているので、シーズンランクも入れようということになった」と話した。(連盟のコメント)
若い選手が移行しているから、という理由は全うに見えるが、それは確実に枠が取れている場合による。
若い人を入れたいのであれば、それは2人で3枠取れる選手が選抜されている場合であって、若い選手にチャレンジさせて、枠を減らしてしまったら、元も子もない。
そんなゆとりがここのところの女子にあったのか。
GPFに一度優勝している紀平さんですら、ワールドは表彰台に乗った事がない。
坂本選手もようやくこのシーズンにGPFに出られるような安定した。
成績が取れるようになったが、樋口さんですら、まだまだ安定していない。
そうなると一番浮き沈みが大きくなかったのが、三原選手であった。
平均して合計得点を200点以上取れている。
200点台を平均して取れているのは、坂本選手と三原選手のみ。
全日本では惜しくも4位だったが、それでも200点は越していた。
そうした場合は多くは五輪とワールドの選出を分けるのだが、
今回は全日本で表彰台に乗った、河辺選手一本にした。
今回3枠取れたのは、ラッキーとしか言いようがない。
何故なら、ロシアが不参加だったからだ。
今回、ドーピング、ウクライナ問題がなければ、たぶん坂本選手は3位か4位。
樋口選手が11位+3=14位。
これでアウトだった。
ただ、三原選手が四大陸と同じ点数を取れていたら、表彰台に乗れていた。
ロシアがいても6位か7位
これだったら、安全圏内だったはず。
一体何の目的の選考基準だったのか。
これでは為末さんの言う、「弱体化」まっしぐらではないか。
選抜には責任も伴います。いわゆる任命責任というものがそれにあたります。ある世代を境目に密室で決めたがるか、オープンに決めたがるか分かれているように思いますが、それは開かれた世界をイメージするか閉じた世界をイメージするかの違いではないかと思います。密室で決めたがるのはなぜかというと、その人をなぜ選抜するかという理由が貸し借りや複雑な人間関係がありすぎてあまりにも複雑なので、説明しづらいからだと考えています。(為末ブログ)
選抜に対する任命責任というのが、まったくないのか、
それとも選抜の選手に意味があるのか。
もし、これで枠が2つになったら、その選手は心に深い傷を負い、立ち直れなくなったらどうするのか。
こうなると選ばれた選手というより、選んだ側に大きな問題があると
思わざるを得ない。
枠を重要視しすぎて、いつも同じ選手では、と思うかもしれないが、そのいつも同じ選手が死に物狂いで努力して、「いつも同じメンツ」なんである。
羽生さんだって、昌磨だって昼寝していたら、あの成績は残せない。
彼らには、選ばれていない選手以上の努力があるから、定位置でいられたのだ。
スポーツの為の連盟なのか、連盟のためのスポーツなのか、もはやよくわからない状態になっている。
選抜システムは権力である、と為末氏は語る。
それはスポーツ界でも、普通の社会でも同じ事だ。
会社でいう人事権だ。
会社では人事を掌握したものが権力を持つ。
どの世界でも一緒なのかもしれない。
ただ、悪用しようとすると、企業はコンプライアンスが働くし、株主が許すかどうかという問題があるので、ある程度の自浄効果はある。
しかし公益財団法人は、株主はいない。
公平性を語らなくても、権力の座に居座っていられる人間たちが巣くっている。
今までラッキーで済んでいたが、これがすまなくなったらどうなるのだろうか。
【今日の独り言】
しかし、来年以降どうなるのか、世界のフィギュア界。